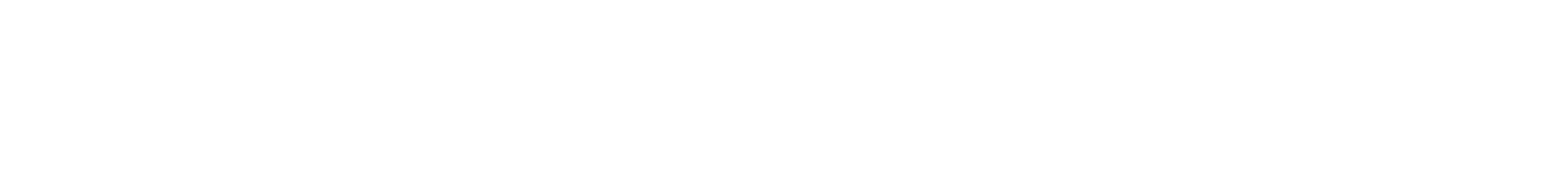第4回定例会一般質問 目次
- 広報PRについて
- 居住支援法人・見守り・空き家問題について
- 海老川上流地区土地区画整理事業・医療センター建替えについて
◆中谷あやの 議員
中谷あやのです。よろしくお願いいたします。
3番目の広報PRについて、最初に質問をさせていただきます。
本市の広報活動として、公式サイトや広報ふなばし、ふなっぷやマチイロなどのアプリ、X・インスタなどのSNSと様々な活動がありますが、市の広報活動の主な目的をどのように設定しているかと、それぞれの役割について教えてください。
また、具体的な指標や成果についてと、SNSアカウントの運用方針、フォロワー数やエンゲージメントの現状、また、これらの広報活動に充てられているそれぞれの年間予算と、担当する部署や人員体制はどのようになっているかについて伺います。
[市長公室長登壇]
◎市長公室長(福田鉄広)
お答えいたします。
市では、市民の皆さんに必要な情報を、広報ふなばしや市ホームページ、SNSなど様々な媒体を活用して、分かりやすくお知らせすることを目的に日々情報発信を心がけているところでございます。
広報ふなばしは市の広報の中核をなすものと考えておりまして、紙媒体に加え、市ホームページやアプリ──マチイロですね、マチイロなどのデジタル媒体でもご覧いただけるようにしております。
また、近年は若い世代を中心に情報の取得手段が多様化しているため、即時性や拡散性の期待のできるSNSを活用した情報発信にも取り組んでいるところでございます。
SNSアカウントの運用方針についてですが、船橋市ソーシャルメディアガイドラインを平成26年に定め、正確で継続的な情報発信、誤解を招かない表現、発信時期の工夫など、SNSを利用する際の基本的な考え方や留意点を示し、適切に活用するよう各課に周知しているところでございます。
また、SNSのフォロワー数などの現状ですが、令和6年11月現在で、公式LINEの登録者数は約2万8000人、フォロワー数はXが約3万2000人、ユーチューブが約8,900人、フェイスブックが約5,700人、インスタグラムが約1,600人となっております。また、投稿を見た方が「いいね」やコメントなどの反応を示した数を示すエンゲージメントにつきましては、令和6年度11月現在で、Xが約45万回、フェイスブックが約1万2000回、インスタグラムが約2,000回となっております。
最後に、令和6年度予算についてですが、広報ふなばしの発行や配布などにかかる費用が約1億800万、市ホームページの管理運営などにかかる費用が約1000万となっておりますが、SNSの運用につきましては特段費用はかかっておりません。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
SNS運用については費用がかかっていないとのことですが、職員の皆さんだけでよくやっていると思います。SNSに関しては別途予算を取って取り組んでもよいのではないかと思います。
また、SNSの市民参加型の双方向のコミュニケーションについては、もっと創意工夫が必要かと思います。
本市の広報の取組についてお伺いしたところ、各課に広報取扱主任を指名し、課長補佐をその職に充てているとのことでしたが、どのような活動をしているのか伺います。
また、AIアドバイザーが就任されたように、広報PRの専門家に広報アドバイザーとして就任していただき、職員向けの研修相談業務を通年行っていただくのはいかがでしょうか、ご見解を伺います。
[市長公室長登壇]
◎市長公室長(福田鉄広)
お答えいたします。
広報課では職員向けに広報マニュアルを作成し、年1回広報主任研修を行い、広報紙や市ホームページ、SNSなどによる情報発信や報道機関への情報提供について、現役の新聞記者などを講師として招き、研修を実施しております。
また、SNSなど若い世代に向けた情報発信力を高めるため、若手職員の指導にも力を入れておりまして、例えば、企業の広報担当者などを講師に招いて年2回研修を実施し、広報力の強化を図っております。
これらを通じまして、各課の広報取扱主任が中心となり、市の公式Xやフェイスブックなど、広報課が運営するSNSについて各課に活用していただくなど、効果的な発信を心がけております。
議員ご提案の広報PRアドバイザーの起用につきましては、現在では起用は考えておりませんが、職員一人一人が広報マンとして事業や市の魅力を発信し、新聞、テレビ、ミニコミ誌などの各種メディアへ数多く取り上げていただいていることもあり、広報課による研修の実施や取材対応への助言、メディアに取り上げられた際の情報共有など、様々な取組を継続をさせていただき、さらに情報発信力を高めていこうと考えております。
今後も広報取扱主任を中心に、必要な情報を必要とされている市民の皆様へお届けできるよう、関係課と連携を密にして情報発信に取り組んでまいります。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
情報発信についてですが、各課の運用にばらつきがあるので、市民目線で読みやすい投稿を心がけていただけるよう要望いたします。特に防犯や防災情報は、SNSで流れてきたときにクリックを押さなくても読めるようにしていただければと思います。市民の皆様に必要な情報がしっかりと届くように対応していただくことを要望いたします。
次に2番目、居住支援法人・見守り・空き家問題について伺います。
今年の5月、高齢者の孤独死6.8万人、警察庁の調査という報道がありました。2050年の推計では、単身世帯が約44%となり、中でも身寄りのない独居者が増加しております。
近年では、孤独死などの不安から単身高齢者が家を借りられないなどの問題が起きています。その一方で、空き家が増えています。住む家を借りられない人が増える中、住む人がいない空き家が増えている。これらの問題を解決する手段として、国がつくった制度が住宅セーフティネット制度、居住支援法人です。国では居住支援法人の活動を推進していますが、まだまだ認知が広がっておりません。
そこで伺います。本市を活動エリアとする居住支援法人は幾つあるか、居住支援法人とどのような連携をしているのかについて伺います。
[建築部長登壇]
◎建築部長(木村智)
千葉県の指定を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人のうち、船橋市を活動エリアとしている法人は現在24法人あります。本市におきましては、平成29年5月に船橋市居住支援協議会を設立し、同年7月には相談窓口「住まいるサポート船橋」を開設し、住宅確保要配慮者の居住支援に取り組んでいるところであります。
この相談窓口事業を実施する中で、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けている法人に協力を仰いでいる事例もあり、また、福祉部局においても協力を得ていると聞いております。
また、住宅政策課も参加している、福祉サービス部で実施しております住まい支援システム構築に関するモデル事業の住まい調整会議には、住宅確保要配慮者居住支援法人として4法人にご参加いただいております。
今後につきましても、各法人の事業内容を生かした連携を図っていきたいと考えております。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
居住支援法人と正式な連携が始まったとのこと、よかったです。今後、居住サポート住宅の認証制度が始まりますが、居住支援法人との連携が不可欠ですので、引き続き連携が深まるよう取組をお願いします。
居住支援法人の役割は3つに分けますと、入居前の住宅を探すこと、入居後の見守り、死後事務です。孤独死など様々な不安から家を貸すことができない大家さんに、居住支援法人が見守りや死後事務を行うことで安心していただき、家を借りることができます。
本市での孤独死に対する現状の把握と取組についてお伺いしたところ、孤独死について状況を把握していないとのことで大変驚きました。今後は把握していただくよう要望いたします。
資料で配付しておりますが、船橋警察署に自宅で1人で亡くなった方の人数について確認を取りました。今年1~9月では男性が234人、女性が101人でした。本市も孤独死ゼロを目指し、孤独死の状況把握と予防に取り組んでいただきたいと思います。
孤独死の予防のため、本市の緊急通報装置貸与事業は、見守りの1つの方法かと思います。これはどのような制度か、通報があったときの対応や業者の選定方法、緊急通報装置を貸与している方に対して、貸与以外にどのような支援を行っているかについて伺います。
[高齢者福祉部長登壇]
◎高齢者福祉部長(滝口達哉)
お答えいたします。
緊急通報装置貸与事業につきましては、在宅の日常生活に支障がある独り暮らし高齢者などに対して、急病など万一の場合に受信センターと緊急連絡が取れる通報装置本体とペンダント、熱感知センサーの一式を貸与するもので、利用者が緊急ボタンを押した場合や24時間熱感知センサーが作動しなかった場合に、受信センターから本人への呼びかけを行い、警備員が駆けつけ、必要に応じて救急隊への出動要請などを行っております。
現在、プロポーザルで選定した委託事業者と5年間の契約を締結し、貸与数は約2,100件であり、年間約1,500件の通報に対応しております。
緊急通報装置以外の見守りの支援についてでございますが、安否確認と孤独感の解消のための声の電話訪問事業や、お弁当をお届けするとともに安否確認を行う食の自立支援事業がございます。
また、本市全体では、地域の誰もが高齢者を見守ることができるよう、気づきのポイントなどを掲載した高齢者見守りガイドブックや、高齢者などの総合相談窓口として地域包括支援センターをご利用いただけるよう、センターの連絡先を掲載した地域ごとのチラシを配布しながら、地域での見守り体制の構築を図っております。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
今回お話をお聞きする中で、緊急通報装置を貸与している方がそれぞれどのような支援を受けているかについては、ひもづけていないので把握していないとのことでした。緊急通報装置が必要な方は何かしらの支援や見守りが必要な方なので、貸与している方と支援のひもづけが必要かと思います。
そこでご提案したいのが血流認証ゲートシステムです。写真を配付資料に載せておりますが、こちらは個々の人の指の血流の差を生体認証し、指を鍵にする仕組みで、ご本人、ご親族、介護ヘルパーさん、家事代行や見守り支援の方など、20人まで指の鍵を登録することができ、誰がいつ指の鍵を使って出入りしたのかを確認しながら見守りすることができるシステムです。鍵をなくすことがないので認知症の方や障害者の方も安心して使うことができ、使用料は月額1,800円で、導入が決まった自治体もあります。
また、見守りが必要な方は高齢者の方だけではないので、今後は緊急通報装置貸与事業の対象を広げていくことと、血流認証ゲートシステムの導入を検討していただけるよう要望いたします。こちらに関しては引き続き取り上げていきますので、答弁は求めません。
次に空き家問題についてです。
空き家の原因となる未登記や放置相続を防ぐため、相続登記が義務化され、私の元にも多くのご相談があります。よくあるご相談が、父が亡くなったときに相続登記をしていなくて、名義が父のままになっているけれども、母が認知症というご相談です。認知症になると遺産分割協議ができなくなり、家の売却や貸出しもできなくなります。認知症になって家を売却する場合は、成年後見制度を使う必要があり、成年後見人に報酬を払う必要がありますが、後見人の報酬助成があることを知らない方が多くいます。
そこで伺います。本市の成年後見人の報酬助成制度の説明と助成件数について伺います。
[高齢者福祉部長登壇]
◎高齢者福祉部長(滝口達哉)
お答えいたします。
成年後見人等の報酬助成は、後見人などに報酬を支払うことが困難な場合に、その人の主たる生活の場が在宅の場合は月額2万8000円、施設入所または長期入院の場合は月額1万8000円を上限として助成する事業でございます。
次に、令和5年度の成年後見人等の報酬助成の件数でございますが、在宅の方が26件、施設などの方が96件(後刻「93件」と訂正)、合計119件となっております。
以上です。
[発言する者あり]
○議長(渡辺賢次)
答弁訂正。はい、お願いします。
[高齢者福祉部長登壇]
◎高齢者福祉部長(滝口達哉)
答弁訂正のほう、よろしくお願いします。
先ほどの報酬助成の件数ですけども、私が施設のほうで「96件」と発言しましたが、正式には「93件」でございます。おわびして訂正いたします。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
配付資料に記載しておりますが、家庭裁判所で本市に居住している方の成年後見制度と任意後見制度の利用状況について調査したところ、昨年度は成年後見が179人、任意後見がゼロ人でした。任意後見制度は認知症になっても安心して暮らせるように、元気なうちに準備をして必要なことを自分で決めることができますが、まだまだ利用する方が少ないです。
任意後見制度は、公証役場で任意後見契約を作成し、後見が必要になったら家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人が選任され、監督人に対して報酬の支払いが発生します。この監督人の報酬が任意後見制度の利用の1つのハードルになっているかと思います。
そこで要望なのですが、成年後見の報酬助成のように、任意後見監督人の報酬助成の制度をつくっていただけないでしょうか。令和4年に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画には、任意後見制度の利用促進について、自治体の周知、相談の仕組みづくりが記載されております。家庭裁判所の任意後見制度の利用数はゼロ人でしたが、公証役場で任意後見契約をして、任意後見契約の登記をしている方の数は違いますので、そちらの数の確認もお願いします。
一人暮らしでも身寄りがなくても誰もが安心して年を重ねることができるよう、時代に即した制度が必要です。居住支援・見守り・孤独死ゼロ対策、空き家問題などは、それぞれの部署の縦割りを超えて連携して考えていく課題かと思います。そういったことに大きな枠で取り組める部署をつくっていただければと思います。本市の見解を伺います。
[高齢者福祉部長登壇]
◎高齢者福祉部長(滝口達哉)
お答えいたします。
国の第二期成年後見制度利用促進基本計画において、任意後見制度は私的自治の尊重の観点から、必要最小限の公的な関与を制度化したものであり、市町村は周知・相談の仕組みづくりを中心に役割を発揮するものとあります。
そのために、任意後見監督人の報酬助成制度をつくることは考えておりませんが、引き続きパンフレットの作成や市民向けの講座などを開催することで、周知や相談の仕組みづくりを構築してまいります。
また、見守り・孤独死ゼロ対策、空き家問題を大きな枠で取り組める部署が必要ではないかとのことでございますが、高齢者における地域包括ケアシステムの住まい、予防、生活支援、介護、医療の取組の中で、関係各課との連携、情報共有を図っております。
以上です。
[福祉サービス部長登壇]
◎福祉サービス部長(岩澤早苗)
お答えいたします。
議員ご指摘の居住支援・見守り・孤独死ゼロ対策、空き家問題などを大きな枠で取り組める部署とのことでございますが、これらの諸問題につきましては、関係各部署において事業を実施し対応を図ってきていると考えております。加えて、制度のはざまにあるなど課題が複合化・複雑化した支援ニーズに対応するために、令和5年4月より重層的支援体制整備事業を開始して包括的な支援体制を整えたことにより、関係部署が一堂に会し、対応を検討し、連携しながら解決を図るように取り組んでいるところでございます。
令和5年度の関係各部署を集めた重層的支援会議及び支援会議は合わせて17回開催し、その中の1つの事例として、親族はいるものの頼ることができない、老朽化した住居等の課題を抱えていた一人暮らしの方について、13の関係課や関係機関が一堂に会し、対応を考え、生活の立て直しに結びつくことができた例もございます。
今後も引き続き、庁内連携を密にして取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
任意後見制度については、周知や相談の仕組みづくりに期待しております。また、各部署で連携されているとのこと、承知しました。制度のはざまにある方がどこに相談したらよいか分からないことがないように、誰でも広く相談を受け付ける相談窓口の名前などを工夫していただくことを要望します。居住支援・見守り・孤独死ゼロ対策、空き家問題は今後の大きな課題だと思いますので、引き続き質問してまいります。
次に、江戸川上流地区土地区画整理事業・医療センター建て替えについて伺います。(発言する者あり)ごめんなさい。すいません。失礼いたしました。海老川上流地区土地区画整理事業・医療センター建て替えについて伺います。
現在、1号調整池の工事が止まっておりますが、その理由について教えてください。また、1号調整池については助成金が既に支払われておりますが、助成金申請の流れと支払った期日と金額について教えてください。
[都市計画部長登壇]
◎都市計画部長(杉原弘一)
お答えいたします。
まず、1号調整池に係る助成金の流れについてご答弁いたします。
令和4年8月29日付で海老川上流地区土地区画整理組合から市の助成金交付申請書が提出され、9月27日付で本市は助成金の交付を可とする決定をいたしました。その後、1号調整池の設計等に係る協議に不測の日数を要したことなどの理由により、令和4年度の助成金に係る予算4億8400万円を令和5年度に繰り越しいたしました。
令和4年度申請分の対象工事である1号調整池の鋼矢板の打ち込み、底盤の地盤改良工事が完了したことから、令和6年3月25日付で組合から助成金に係る完了実績報告が提出され、本市において完了検査を実施した分のみについて、5月10日に組合に対し助成金4億8307万円を支出いたしました。
次に、調整池の工事が止まっている理由についてのご質問でございますが、区画整理事業における雨水排水の全体計画が協議中であることから、現在は調整池の工事が行われていない状況でございます。協議が調った後、工事に着手する予定でございます。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
1号調整池の助成金交付可否決定通知書には、1号調整池工事については、設計に関わる下水道部との協議が調い次第、確定した図面及び設計書を提出してから着工することと条件が付されていますが、協議が調ったことを客観的に確認できる書面が提出されておりません。都市政策課に下水道部との協議が調っていることが分かる書面はないか尋ねたところ、大半が黒塗りとなっている打合せ記録簿を頂きましたが、協議が調っているかを確認する書面としては不十分であると考えます。
これは船橋市文書管理規則第6条3項にも関連し、行政の公平性と透明性を確保するためにも、助成金交付において必要な協議書や計画書が整備されているかはとても重要です。
今後は文書管理規則に基づき、下水道部との協議書の作成を求めます。また、本市には雨水貯留施設設計の手引きが定められており、協議成立に必要な添付図書一覧が明確に記載されております。それによりますと、全体の排水計画の提出がない状態では、協議に必要な判断材料が整っていなかったのではないかと思いますが、見解を伺います。
[都市計画部長登壇]
◎都市計画部長(杉原弘一)
お答えいたします。
令和4年度分の助成金交付申請における1号調整池の工事内容は、止水壁となる鋼矢板を池の周囲に取り囲むように打ち込む工事及び底盤の地盤改良工事となっておりました。令和4年度の助成金交付可否決定に当たり、議員のご質問にもございましたとおり、設計に関わる下水道部との協議が調い次第、確定した図面及び設計書を提出してから着工することという条件を付しましたが、これは令和4年度分の対象工事に対しての条件となります。
令和5年4月17日付で組合から、この条件を説明するために必要な鋼矢板及び底盤の地盤改良に係る詳細な書類が添付された、調整池の構造に関する確認についてと題する依頼文書が提出されました。令和5年8月に組合から市に対し、これらの書類に基づき、1号調整池の構造等に関する説明がなされたことから、鋼矢板の打ち込み及び底盤の地盤改良について協議が調ったと判断したものでございます。
調整池に係る協議につきましては、区画整理事業全体における雨水排水計画を一体的に協議することがより望ましいと考えておりますが、土地区画整理事業及び新病院建設の円滑な推進を考慮し、1号調整池の一部の施工について協議を進めてまいりました。
現在は雨水排水の全体計画の協議、その後、個別の調整池の協議という流れで、千葉県や施設の帰属先となる市下水道部との協議を進めており、具体的には令和6年9月9日付で組合から市に対し、雨水排水の全体計画に係る協議依頼書及び関係図面が提出され、これに基づき、組合と下水道部において協議が進められている状況でございます。
この協議の過程につきましては、確定した図面とともに協議が調ったことがより明確に分かるような文書の作成、整理に努めてまいります。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
1号調整池の助成金申請から2年たち、やっと全体の雨水排水計画が出されたとのことです。本来なら最初から出されるべきだったと思います。下水道部との(予定時間終了2分前の合図)協議文書については、これからも助成金申請は続きますので、誰が見ても明確に協議が調ったことが分かるように進めてください。
1号調整池については、万が一、念田川があふれた場合、1号調整池にあふれた水が流れ込んでしまう可能性があるため、追加工事などの何らかの対策が必要であると伺っております。今後どのような対応をされるのか伺います。
[都市計画部長登壇]
◎都市計画部長(杉原弘一)
お答えいたします。
1号調整池の貯留量の算出に当たり、念田川の水が入ることは見込んでいないことから、念田川があふれた水が1号調整池に入る可能性があることについては対策が必要であると以前から認識しておりました。具体的な対策につきましては、現在、組合と協議中でございます。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
念田川があふれた場合、今のままでは1号調整池に水が入る可能性があることが分かったことについては、船橋市民の流域治水に取り組む方や河川や土木の技術者、一級建築士、水道施設建設のエンジニアなどの専門家の方々が時間も気持ちも体力も使って調べて、危険性を指摘したことがきっかけの1つだと思います。今後は市民の皆様が安心できるよう安全に進めてください。
医療センターについてですが、浸水など災害時の病院へのアクセスがやはり心配です。以前の答弁では救急車が通行可能である旨、確認をしているとのことでしたが、災害時は多くの方が徒歩で病院に来ることが想定されます。浸水被害などの心配がなく、どこからでも徒歩で安全にたどり着ける場所に災害拠点病院を建てるべきと思います。
入札辞退により、いつ工事が始まるのか見通しを立てるのは難しい状態だと思います。改めて浸水被害や液状化などの心配がない安全な場所に医療センターを建てれるよう、移転先について再検討を要望します。本市の見解を伺います。
[副病院局長登壇]
◎副病院局長(安孫子勉)
お答えいたします。
これまでの市議会の中でご答弁させていただいた内容となりますが、医療センターの建て替え検討を進めていた当時、用地の確保が大きな課題となっており、現在の計画地は、現地建て替えを含め複数の候補地を検討した結果、まとまった土地を確保できることや、三次救急を担う病院として市の中心部への立地は救急搬送受入れの点でメリットがあること、その他建築条件や来院者の利便性を考慮して移転候補地として選定し、区画整理事業と医療センター建て替えを一体で進めていくことを市として決定したものであります。
新病院予定地は、現在公表されているハザードマップでは、大きな地震による液状化や洪水による浸水想定エリアとなっておりますが、災害拠点病院として必要な施設・設備を整備するほか、免震構造の採用や必要な箇所への液状化対策の地盤改良の実施など、災害時でも医療を継続できる計画としております。
また、新病院の敷地の地盤高さは、現在公表されている、想定し得る最大規模の降雨による浸水予測と区画整理事業により整備される周辺道路計画高さを考慮して設定しています。このため、想定最大規模の降雨でも病院敷地は浸水しないという前提で計画しています。
災害時の病院へのアクセスについては、令和6年第2回定例会でご答弁させていただいたとおり、浸水、液状化ともにハザードエリア外になっている、新病院用地東側の土地区画整理事業により整備される道路からのアクセスを想定しております。万が一、東側の道路が通行できないとなった場合には、ほかの通行可能な道路を選んでアクセスすることを想定し、病院敷地への出入口を複数設ける計画としています。
議員がおっしゃるように、どの方向からでも徒歩でアクセスできるような立地であることにこしたことはありませんけれども、様々な検討を重ねた結果、決定した場所であり、必要な対策を講じ、災害時のアクセス経路も想定していることから、医療センター移転先について再検討する考えはございません。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
移転先について再検討するお考えはないとのことですが、浸水の危険がある場所に総額1000億円を超える病院を造ることに市民の皆様の理解が得られるか疑問です。計画から10年たち環境や状況は変わってますので、ゼロベースに戻って柔軟に……(予定時間終了の合図)終わります。
……………………………………………
出典 船橋市議会会議録