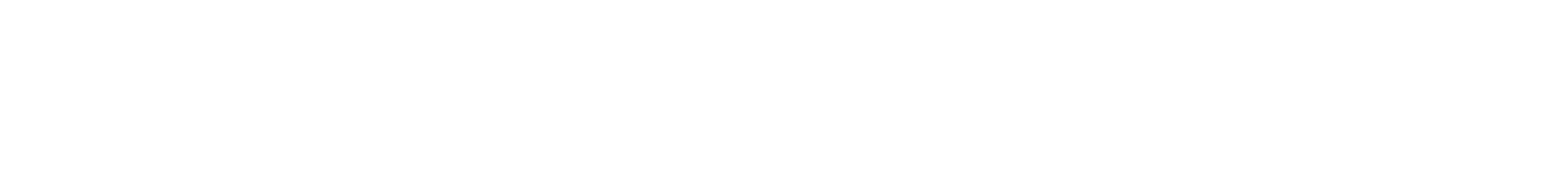第1回定例会 市政執行方針及び議案に対する質疑 目次
- 1.結婚生活支援事業について
- 2.広報PR・デザイン力・職員の適材適所について
- 3.産後ケアについて
- 4.女性起業支援・スタートアップ支援・インバウンド支援について
- 5.高齢者サポート事業・緊急通報装置の貸与・孤独死ゼロについて
- 6.金属スクラップヤード等対策について
- 7.海老川上流地区土地区画整理事業・医療センター建て替えについて
第1回定例会 市政執行方針及び議案に対する質疑のポイント
今回の質疑は、令和7年6月22日に、船橋市長選挙があることもあり、現時点での船橋市の状況や方向性について、特に確認しておきたいことについて質問しました。
◆結婚新生活支援事業について
【質問】
・結婚新生活支援事業の対象拡大や若者・子育て支援の重要性を評価する一方、当初見込んだ164件に対し、現在の申請件数が21件(助成金の支給率10.7%)となっている点について、市の分析や、事前届出要件や周知不足で申請できなかった市民への救済措置の有無を問う。
【回答】
・令和6年度より開始した本事業は、年度末に向け申請が増加する傾向があると他市の状況から見込んでいる。すでに広報や各種案内を通じた周知を実施しており、令和7年度に向けて対象年齢や補助上限額の拡大を検討しているが、令和6年度対象者の救済措置は行わない方針。
【質問】
・初期の事前届出要件や年齢制限(29歳以下)の設定は見通しが甘かったとし、今後の周知強化策について具体的な改善策を求める。さらに、転居時期の要件について、市川市のように引っ越しが多い2月・3月入居者も補助対象とするなど、より柔軟な運用が可能かどうかを問う。
【回答】
・今後は、既存の広報活動に加えて、市公式アプリ「ふなっぷ」や「ふなばし情報メール」などを活用し、より多くの市民への周知を図る。転居時期については、当初の前提(婚姻と同時の住宅契約・転居)を見直し、令和7年度からは前年度の転居者にも家賃補助を実施することで、支援対象を拡大する柔軟な運用を予定している。
◆広報PR・デザイン力・職員の適材適所について
【質問】
・広報ふなばしの配布方法で一部市民に情報が届いていない現状を踏まえ、新年度予算決定後に、市政施策や市民生活に関わる制度紹介を掲載した特別号を作成し、全戸配布すること、また「ふなばし市民便利帳2025年版」と同時に配布することを提案。
【回答】
・新年度の予算案や施策は、既存の広報ふなばしや各種ポスティング、公共施設での掲示、SNS等を通じて周知しているため、特別号を全戸配布する必要は現時点ではない。ただし、来年度のふなばし市民便利帳においては、制度紹介の特集を検討する可能性がある。
【質問】
・X(旧Twitter)の運用について、140文字以内の制限により重要情報が十分に伝わっていないとの懸念を指摘し、システム改修で文字数制限を撤廃するか、もしくは各課の投稿を取りまとめて制限なく発信できる仕組みの整備を求める。さらに、広報課の負担増への対応として、予算確保、人員補充、及びデザイン面の専門人材の採用・配置による広報力強化を要望する。
【回答】
・Xの投稿は、広報課が市民に分かりやすく情報発信するために管理しており、無料範囲での140文字制限の中で運用しているが、必要に応じて有料プランを活用している。システム改修は次回更新時に検討予定である。デザイン面については、他自治体の事例を参考にしつつ、現状は広報課が各課への助言や研修を通じて対応しており、新たな専門部署設置の提案については、広報課で対応。
【要望】
広報課内にデザイン相談係の設置を要望した。
◆産後ケア事業について
【質問】
・通所型産後ケア事業について、生後4か月以降の受け入れ状況と、そのうち助産院での利用件数を、件数ではなく利用日数で確認するよう求めた。
【回答】
・令和6年11月末時点で、90人が延べ185日利用しており、そのうち生後4か月以降の利用日数は93日、助産院での利用日数は27日と回答した。
【質問】
・助産院が産後ケア事業の経営面で厳しい状況にあり、委託料の増額だけでは補えない経費負担や、加算要件を満たせず、一人で運営している現状を踏まえ、家賃補助や国の支援事業を活用した施設の新設・拡充など、長期的な経営支援や補助を求めた。
【回答】
・次年度、物価上昇等を考慮し、全サービスの委託料を増額するほか、令和6年10月発出のガイドラインに基づき安全マニュアルの作成や、生後4か月以降の児に複数名で対応する際の受け入れ加算も実施する。今後は、委託料増額後の各実施機関の状況を見守りつつ、国の支援事業にも注視していくと回答。
【要望】
・産後ケアは母子の健康と地域の子育て環境向上に不可欠であり、本市のさらなる積極的な支援を強く要望した。
◆女性起業支援・スタートアップ支援・インバウンド支援について
【質問(女性起業支援)】
・女性限定の起業セミナー・交流会について、どのような支援内容が盛り込まれているか、また、3月1日の女性起業交流会の参加者数、周知方法、具体的なプログラム内容を確認。
【回答】
・令和7年度予算で、船橋商工会議所の「ふなばし起業スクール」への参加を促す女性限定のセミナー・交流会を企画。3月1日の交流会は、2月25日時点で37名の申込みがあり、広報ふなばし、市ホームページ、SNS、ダイレクトメールなどで周知。交流会では、参加者を小グループに分けたグループワークが実施される。
【要望】
・交流会で起業希望者や起業中の女性に対して、必要な支援を把握するためのアンケート実施など、今後の支援策に活かす取り組みを求めた。
【質問(スタートアップ支援)】
・宮崎市のインキュベーションルームの事例を踏まえ、本市の起業支援施策として、インキュベーション施設やコワーキングスペースの現状と今後の展開について確認。
【回答】
・市は、中小機構や千葉県と連携し「ベンチャープラザ船橋」を設置、35室中33室が入居しており、起業者支援に寄与している。加えて、民間のワーキングスペース・レンタルスペースも市ホームページで紹介し、関係機関と連携しながら、既存施設のさらなる活用や新設の可能性を調査する予定。
【要望】
・ベンチャープラザ船橋のみでは不十分であり、より多くの起業家が相談や交流できる拠点の整備を、東京都の充実した支援施策と比較しながら、充実を強く要望。
【質問(インバウンド支援)】
・成田空港拡張に伴うインバウンド需要の増加を背景に、船橋市としてどのように外国人観光客の誘致・支援に取り組むかを確認。
【回答】
・市は、立地の強みを活かし、魅力発信サイト「Funabashi Style」や多言語対応リーフレット、船橋駅前インフォメーションセンターでの指差し確認シート活用など、各種施策を実施。また、外国人観光客向け店舗のリーフレットを成田空港内で配布する予定で、SNS等を活用して情報発信に努めている。
【要望】
・インバウンド対策は単一施設ではなく、地域全体で連携し一貫した観光支援を行うことが不可欠であり、地域経済の活性化やリピーター増加を目指し、全体的な取り組みの強化を要望する。
◆高齢者サポート事業・緊急通報装置の貸与・孤独死ゼロへの取組
【質問】
・緊急通報装置利用者の状況や、支援体制との連携の具体的取り組み、さらに利用者が賃貸住宅か自己所有不動産かの内訳を確認するよう求めた。
【回答】
・令和6年11月末時点で約2,200人(正確には2,175人)が利用中で、利用者の約65%は要介護認定を受け各種介護サービスを利用、残り約35%は軽度生活援助員等のサービスを組み合わせて支援している。賃貸住宅と自己所有不動産の内訳は全数把握できていないが、今後調査を進めると回答。
【要望】
・利用者の居住形態の把握は「身寄りのない高齢者等サポート事業」と連携して必要であり、調査の実施を要望。また、本事業の対象要件において、自己所有不動産に住む方も見守り支援の対象となることを明示し、広報や窓口で丁寧に周知するよう求めた。
◆金属スクラップヤード等対策について
【質問】
・医療センター移転予定地近隣のスクラップヤードについて、市内に何カ所あるか、また市民の安全・環境面の懸念に対し、どのような対応を行っているかを問う。
【回答】
・市内には現時点で金属スクラップヤードが17カ所ある。千葉県の規制条例に基づき、定期的な現場確認や関係部署との連携を通じて、保管基準違反や公害の疑いがある場合には、現地調査や立ち入り検査を実施していると回答。
【質問】
・念田川の土砂がタリウムに汚染されているとの懸念に対し、市民から調査の申し入れがあっているが、具体的な対応方針を示すよう求めた。
【回答】
・念田川周辺のスクラップヤードからの排水については、特定事業場等に該当せず検査は実施していないが、定められた測定点で定期的に水質調査を行い、現時点では異常は認められていない。今後も状況に応じた監視・調査を継続する。
【要望】
・医療センター用地周辺の市民の不安を解消するため、さらなる監視と調査の強化を要望。
海老川上流地区土地区画整理事業・医療センター建替えについて
【質問(土地区画整理事業 助成金)】
・各年度の助成金の内訳、既に支払いが完了している助成金の金額・支払い時期、及び未使用の助成金の取扱いについて確認を求めた。
【回答】
・令和4年度申請分(4億8,400万円)は調整池の築造費等のため、令和5年度へ繰り越し、令和6年3月に一部工事完了報告後、令和6年5月に約4億8,307万円を支払済み。
・令和5年度申請分(8億4,820万円)は一度令和6年2月に7億3,380万円へ変更申請後、令和7年1月に再度内訳調整の変更申請中。
・令和6年度申請分(15億1,120万円)も令和7年度へ6億9,340万7千円に変更申請中。
・令和7年度当初予算は10億4,413万8千円を見込んでおり、各年度の支出済み分・繰越分を除いた額が不用額となる。
【要望】
・変更・繰越・不用額が混在し分かりにくいため、申請書類や協議書を明確に整備するよう要望。
【質問(医療センター建替え)】
・入札不調を受けた医療センターの建替えスケジュールの見直し、現病院の耐用年数や老朽化を踏まえた維持管理・修繕計画、及び医療機能維持のための優先順位や具体策、建替えまでの課題と対応策について確認を求めた。
【回答】
・入札中止を受け、建替えスケジュールおよび事業の進め方を再検討中。
・現病院は令和9年度開院を前提に、従来通り維持管理委託や設備更新・修繕を計画しており、即時の対応は不要とするが、建替えの遅延に伴い今後必要な見直しを実施する。
・更新・修繕は計画的に行いつつ、特に老朽化が深刻な排水管等は大規模工事が必要となる場合があるため、技術職員による日々の点検・補修を継続していく。
【要望】
・早期建替え実現に向け、柔軟な対応と安全かつ迅速な建替え方法の模索を強く要望。
船橋市議会の会議録へのリンク
会議録の内容
◆中谷あやの 議員
おはようございます。中谷あやのです。どうぞよろしくお願いします。
まず初めに、新年度予算で骨粗鬆症検診を盛り込んでくださったことに感謝申し上げます。船橋市にお住まいの女性の健康を守るための大切な取組の1つになるかと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
では、通告の4を2の前に、7を5の前に入れ替えて質問させていただきます。
結婚新生活支援事業についてですが、対象年齢など事業を拡大したことを高く評価します。本市の年少人口が減少している中で、若者支援、子育て支援はとても大切な取組です。より多くの市民の方々に助成できるようになることはとてもよいことだと思います。よい事業をつくることとそれを多くの市民の方々に知ってもらうことは、どちらも欠かせない両輪であり、どちらが欠けても支援の充実、市民サービスの向上にはつながりません。この事業は当初164件の助成件数を予定していましたが、現在の助成件数は21件で、予算額に対する助成金額の割合は10.7%とのことです。この点について、本市はどのように分析しているのか伺います。
また、執行できなかった予算を救済措置に充てられないでしょうか。当初、事前届出が要件だったことから、申請を断念された方や、本市の周知不足により要件を満たしていたにもかかわらず、制度を利用できなかった市民の方々への救済措置が必要と考えますが、市の見解を伺います。
[建築部長登壇]
◎建築部長(木村智)
結婚新生活支援事業は、本市では令和6年度より開始した事業であります。現在の申請状況は当初の見込みよりかなり低くなっておりますが、既に開始している他市の状況を見ますと、年度末に向けて申請数が増加する傾向があり、本市においても実際に問合せが増加してきているところでございます。
令和7年度は、現在の申請状況や問合せ状況を参考に、事業の目的に照らし、制度内容について改めて検証を行った結果、対象年齢や補助上限額を拡大いたしますが、令和6年度の同事業の周知につきましては、広報ふなばしや市ホームページへの掲載、市役所1階の戸籍住民課や船橋駅前総合窓口センター、各出張所等へのパンフレットの配架、市役所本庁舎1階の電子掲示板への掲載、X、インスタグラム、ユーチューブへの投稿を行ってまいりました。また、市内宅地建物取引業者団体に、各不動産店への案内チラシの配付を依頼したところであります。
このように様々な方法による周知を行ったことにより、自身が対象者であることに気がつかなかった方や当初申請を諦めた方への周知も行えたものと考えておりますので、令和6年度事業の対象者になり得た方々を令和7年度に支援の対象とすることは考えておりません。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
令和6年度事業の対象者になり得た方々を支援の対象とすることは考えていないとのことですが、事業スタート時に事前届出を要件としたことや年齢を29歳以下としたことなど、事業の見通しが甘かったと思います。現状を正しく振り返り、課題を分析し、その原因を明確にすることで初めて具体的な改善策を講じることができると思います。今後の周知について、より多くの市民の方々に知っていただくための改善策について、市の考えをお示しください。
続けて、転居時期の要件について伺います。
市川市では、市長の定例記者会見で、若者が結婚しやすい環境を整えるとともに、将来的に子育て世代となる若者を市内に呼び込み、定住を促す目的で、新婚時のみならず、結婚準備段階で同居を開始するカップルに対しても補助をする新しい制度を導入すると発表しました。この事業は4月1日から開始される予定ですが、引っ越しが多い3月入居のカップルも補助対象とし、柔軟な対応を取るとしています。本市においても、市川市のように引っ越しの多い2月、3月入居の場合も補助対象とするなど、より柔軟な運用を行うことはできないか、市の見解を伺います。
[建築部長登壇]
◎建築部長(木村智)
今後の周知につきましては、先ほど答弁いたしました方法に加えて、新たに市公式アプリである「ふなっぷ」への掲載やふなばし情報メールの中で、市内の事業者を主な対象者とした事業者情報メールへの掲載を検討しているところであります。今後もより多くの方への周知に努めてまいります。
また、転居時期の要件についてでございますが、本事業は、当初結婚の時期と住宅確保の契約及び転居時期がほぼ同時となることを前提とし、当該年度内の住宅契約を要件として開始いたしました。しかしながら、実際には婚姻届の前に同居する例も数多くあり、結婚と転居の時期は様々でありますことから、令和7年度事業におきましては、当該年度以前の転居も支援の対象といたします。具体的には、当該年度以前に転居した方には、当該年度内に発生している家賃を補助することで、住居確保の初期費用同等の補助ができる形にする予定であります。
このことから、令和7年度は、結婚新生活を開始する若者世帯の居住に関し、より幅広い支援が行えるものと考えております。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
転居時期の要件については大変柔軟なご回答をいただけたと思います。新しい事業や拡大する事業は、スタート時の周知がとても大切です。関心のある市民の皆様が自分には当てはまらないと諦めてしまうことのないよう、間口を広げ、周知を徹底し、市民に寄り添う市政運営を引き続きお願いいたします。
次に、広報ふなばしについて伺います。
市民の皆様にとって、市の予算は、今後の市政運営の方向性を知る重要な情報であり、生活に密接に関わるものです。しかし、現在の配布方法では、一部の市民の方々に情報が届かない状況が発生しています。
そのため、新しい年度の予算が決定した後、市の施策や重点事業を広く周知するための市の予算概要、市民生活に関わる影響、市民の皆様が活用できる制度の紹介などを掲載した特別号を作成し、市内の全世帯に配布するのはいかがでしょうか。また、ふなばし市民便利帳2025年版を全戸配布する際に、予算決定後の特別号を一緒に配布できないか、伺います。
[市長公室長登壇]
◎市長公室長(福田鉄広)
お答えいたします。
新年度の予算案につきましては、例年、広報ふなばし3月1日号で市政執行方針として掲載しておりまして、市の施策や重要な事業を市民の皆様にお伝えしております。また、新年度の予算は4月1日号で紹介しており、その他の市の新規事業などは、その都度、担当課と相談しながら周知を図っているところでございます。
なお、広報ふなばしは、新聞折り込みを中心に新聞を取っていない人のためのポスティングや、公共施設、駅などへの広報スタンドの設置、また、市のホームページをはじめ、XやフェイスブックなどのSNSを通じて発信しており、多くの市民の皆様に市の情報が幅広く届くように取り組んでおります。
こうしたことから、議員ご提案の広報特別号を作成しての全戸配布につきましては、現時点では考えておりませんが、来年度発行予定のふなばし市民便利帳につきましては、全戸配布を行っていく中で、市民の皆様が活用できる制度について所管からの意見を聞き取り、ふなばし市民便利帳に特集を組むことが可能であることから、検討してまいりたいと考えております。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
ふなばし市民便利帳に特集は組めるとのことですので、ぜひ前述の結婚新生活支援事業についても特集を組んでいただけるよう要望します。
次に、Xの運用について伺います。
本市のSNSの中で、Xは最もフォロワー数が多く、災害時などの緊急情報を市民へ迅速に届ける重要なツールです。現在本市のX投稿には140文字制限のあるものとないものが混在し、不審者情報や災害情報など重要な情報が制限内となっています。広報課以外の課が投稿する際、システム上の制約で140文字以内となると伺いましたが、情報が十分に伝わらず、市民の方からも分かりづらいとの声が寄せられています。画像添付など改善はされていますが、依然として情報不足の懸念があります。
そこで伺います。システムを改善し、文字数制限を撤廃することは可能か。また、難しい場合は、各課の投稿を取りまとめ、制限なく投稿できる仕組みを整備できるか、お伺いします。
[市長公室長登壇]
◎市長公室長(福田鉄広)
お答えいたします。
Xにつきましては、各課の職員が市のホームページ作成システムから投稿し、広報課が市民の皆様に分かりやすく伝わるように、表現や添付する画像などの確認を行った上で、市公式Xとしての情報発信に努めているところでございます。Xの規約では、140文字以内が無料で投稿できる文字数となっておりまして、市では無料の範囲内を基本として現在運用をしているところでございます。ただ、それとは別に、広報課が140文字以上で投稿できる有料プランに加入しておりまして、市ホームページ作成システムを経由せずに直接投稿することも可能なことから、各課において140文字以内では市民の皆様に正確に伝えることが難しい場合には、広報課へ相談していただくよう、研修などを通して周知を図っているところでございます。
また、文字数制限をなくすにはシステム改修が必要であると、市のホームページ委託事業者からも回答がございましたことから、現時点での対応は難しいと考えておりますが、次回のシステム更新時に対応可能かを検討してまいりたいと考えております。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
広報課を通じて140文字以上の投稿が可能とのことですが、職員の皆さんの負担増が懸念されます。広報課はSNSの予算が少ない中で運用に尽力され、ご担当者の皆様は大変頑張っておられると思います。今後は予算を確保し、人員補充やシステム改修に取り組むよう要望いたします。
次に、デザイン力・職員の適材適所について伺います。
自治体の広報では、SNSや各種媒体を活用した情報発信が重要であり、デザインの質が市民の関心を引く鍵となります。デザインの仕事は、もともと持っている素質や才能、向き不向きが大きく影響する分野であり、民間では専門職が担う分野です。本市では、予算のない事業などではデザインの専門知識のない職員が兼務し、試行錯誤に時間を要し、本来の業務に支障が出ているケースもあるのではないでしょうか。他自治体では、デザイン・クリエイティブ枠採用を行っている事例もありますが、本市としても、デザインの専門人材を積極的に採用し、デザイン専門の部署をつくるなど、適材適所の配置を進めることで、より効果的な広報活動を展開することができると考えますが、本市の見解を伺います。
[総務部長登壇]
◎総務部長(鈴木幸雄)
職員の採用につきまして、一部の自治体において、デザイン・クリエイティブ枠での採用を実施しているということは把握をしているところでございます。現時点で、本市はそうした枠での採用は実施していませんが、市の施策に関する情報を市民の皆様にお伝えしていくことは非常に大切なことであると考えており、そうした専門枠での採用による効果等について他自治体の情報を収集してまいります。
また、新たな専門部署の設置をという組織に関するご提案についてでございますが、現在も市全体の広報力の強化につきましては広報課が担っているところでございますので、引き続き、広報課において各課への研修や助言などを行っていくものと考えているところでございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
新たな専門分野ではなく広報課で行うとのことですが、ぜひ広報課の中にデザインの相談や作成を依頼できるデザイン係をつくっていただくことを要望します。職員の方々が気兼ねなくデザインについて相談できる環境を整えていただけるようご検討をお願いいたします。
次に、産後ケア事業について伺います。先番議員から質問がありましたので、通所型の産後ケアに絞って伺います。
利用数が大幅に増加しているとのことですが、生後4か月児以降の受入れは、利用数のうち何件か。そのうち助産院の利用は何件か伺います。
[健康部長登壇]
◎健康部長(高橋日出男)
お答えいたします。
利用件数のうち、生後4か月児以降の受入れは何件かというご質問でございますが、利用期間中に生後4か月を超える場合もございますので、利用日数でお答えさせていただきます。通所型産後ケア事業については、令和6年11月末現在では、90人の方が延べ185日利用し、そのうち生後4か月児以降の利用日数は93日でございます。そのうち27日が助産院での利用日数となっております。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
病院は空きベッドを活用して産後ケアを行っていますが、助産院での産後ケアは個室を備えた施設も多く、お母さんがストレスなく過ごせる環境を提供しています。また、精神的なサポートも手厚く、産後の不安軽減に大きく貢献しています。一方で、助産院は医療機関と比べて産後ケア事業だけで売上げを立て、家賃や経費を払っていく必要があります。
次年度から生後4か月児以降の受入れ加算7,000円が始まりますが、内容と要件について伺います。
[健康部長登壇]
◎健康部長(高橋日出男)
お答えいたします。
まず、内容についてでございますが、生後4か月児未満と同様に、産婦の身体的・心理的ケア、適切な授乳や育児の手技についての指導及び助言などとなります。
要件については、1点目といたしまして、4か月児未満の受入れも行っていること、2点目として、母親のケアのほか、児の保育等の対応のため2名以上でケアを実施すること、3点目として、その対応に当たる従事者リストを作成することなどを要件としております。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
要件について分かりました。
先日、市の委託を受ける助産院から経営が厳しいとの相談を受けました。4月まで予約がいっぱいで週6日フル稼働で産後ケアに尽力していますが、委託料の中から家賃、食事、おやつ、おむつ、ミルク、お尻拭き、衛生用品、消毒用品、電気・水道・ガス代、助産師会への会費、損害保険の加入などの必要経費を払っています。委託料が1,000円増額とのことですが、厳しい状況は変わりません。また、1人で運営しているため、加算要件を満たせません。お母さんたちに癒やしを提供したいと高い志を持って始めた事業ですが、この状況が続くと助産師さん自身が疲れ果ててしまわないか心配です。
長期的に継続するには、経営支援や補助が必要です。本市は利用環境整備に努めるとのことですが、産後ケア専門の助産院に対し、家賃補助や国の支援事業を活用した施設新設、拡充の補助を求めますが、市の見解を伺います。
[健康部長登壇]
◎健康部長(高橋日出男)
お答えいたします。
委託料につきましては、今年度実施機関にアンケートを実施し、各実施機関の状況を把握した上で、物価上昇等を踏まえ、3つのサービス型全てにおいて、次年度委託料を増額することといたしました。
また、令和6年10月発出の産後ケア事業ガイドラインにおいて、安全に関する内容について記載が追加されたことから、本市においても次年度に向け、国のガイドラインに沿って安全マニュアルを改めて作成するとともに、寝返りやつかまり立ちができる月齢に対応する場合の事故防止や安全対策のため、生後4か月以降の児に複数名で対応した場合の受入れ加算も行います。今後は委託料増加後の実施期間の状況を見守るとともに、引き続き、国の支援事業についても注視してまいります。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
産後ケアの充実は、母子の健康を守り、地域の子育て環境向上にもつながります。産後ケア事業は、介護事業や福祉事業と同じように自治体が支えるべき重要な事業です。本市の積極的な支援を強く要望します。こちらについては、今後も引き続き質問させていただきます。
次に、女性起業支援、スタートアップ支援、インバウンド支援について伺います。
まず、女性のための起業セミナー、交流会の予算計上ありがとうございます。こちらの予算でどのような内容の支援をお考えか伺います。また、3月1日の女性起業交流会の開催も予算が少ない中で工夫していただき、所管部門のご尽力に感謝申し上げます。現時点での女性起業交流会の参加者数と周知方法、具体的な内容について伺います。
[経済部長登壇]
◎経済部長(市原保紀)
お答えいたします。
女性のための起業セミナー、交流会は、船橋商工会議所が実施をいたしますふなばし起業スクールへの参加を促すことを主眼に置き、女性が参加しやすいよう参加者を女性に限定したセミナー、交流会を開催するものでございます。女性の先輩起業家による講演や女性同士で起業に関わる悩みなどを共有できるようなものとなるよう、具体的な事業内容を検討してまいります。
次に、3月1日に実施予定の女性交流会についてでございます。
2月25日の時点の応募者数は37名にお申込みいただいてございます。周知に関しては、広報ふなばし、市ホームページへの掲載、Xへの投稿のほか、これまでのふなばし起業スクール受講生に対するダイレクトメールの送信などを行っております。交流会では、講師サポートの下、参加者が4~5名に分かれ、幾つかのテーマに沿ってメンバーを組み替えながらグループワークを行うことを予定してございます。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
3月1日の交流会では、起業したい女性、起業している女性にとって、どのような支援が必要かアンケートを取るなど、今後の女性起業支援に生かしていただけるよう取り組んでいただければと思います。
次に、スタートアップ支援について伺います。
市民環境経済委員会の行政視察で、宮崎市が開設したインキュベーションルームの視察をしておりますが、インキュベーションルームやコワーキングスペースについて、本市の見解を伺います。
[経済部長登壇]
◎経済部長(市原保紀)
お答えいたします。
市としましても、起業を考えている人、起業間もない事業者にとって事業活動を行う場所の確保や、起業後の伴走支援は重要であると認識してございます。
本市では、中小機構及び千葉県と協力し、インキュベーション施設であるベンチャープラザ船橋を設置してございます。ベンチャープラザ船橋では、インキュベーションマネジャーが入居企業の経営支援を行っており、全35室のうち33室の入居があるなど、ニーズの高い施設となってございます。また、市内には民間企業等が運営をするワーキングスペース、レンタルスペースが複数あり、これらの施設を市ホームページで紹介してございます。
まずは関係機関と連携しながら、ベンチャープラザ船橋など、今ある施設をより多くの起業家にご活用してもらえるよう取り組むとともに、新たなインキュベーションルームやコワーキングスペースの設置について、ニーズや先行事例を調査してまいりたいと考えてございます。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
ベンチャープラザ船橋だけでは、これから起業したい方が起業の相談をしたり、起業仲間と出会う場所としての役割は不十分かと思います。もっと幅広く起業にチャレンジする方々を応援する場所が必要です。船橋市に住んでいるけれども、東京のインキュベーション施設を利用している方は多くいます。東京都は、事務所のレンタル、起業相談、セミナー、資金調達、補助金、海外視察など、若い起業家や女性起業家を含め、起業家を応援する仕組みが充実しています。船橋市は東京に近いので、起業家の皆さんは東京と比べています。このままでは優秀な起業家がどんどん東京に流れてしまい、法人税や雇用も東京に流れてしまいます。東京都の起業支援は予算が桁違いなので、同じことをすることは難しいですが、スタートアップ支援は未来の船橋市をつくる大切な事業ですので、今まで以上にスタートアップ支援を充実していただけるよう要望します。
次に、インバウンド支援について伺います。
成田空港の拡張事業が計画されており、千葉県全体の経済や観光産業に大きな影響を及ぼすことが予想されます。2029年の完成を目指し、空港の発着容量が大幅に拡大することで、インバウンドの増加も見込まれます。成田空港の拡張という大きなチャンスを生かし、本市がインバウンド対策を強化することで地域経済の活性化につながると考えます。本市として、インバウンド支援に対しどのように取り組むお考えか伺います。
[経済部長登壇]
◎経済部長(市原保紀)
お答えいたします。
本市は、議員ご紹介のとおり、成田空港と羽田空港の中間に位置し、外国人観光客が興味を引く居酒屋文化を楽しみ、感じられる飲食店も多数存在し、インバウンド需要を取り組む潜在的な可能性を秘めていると考えてございます。
インバウンド対策といたしましては、魅力発信サイトFUNABASHI Styleや市を紹介するリーフレットの多言語化による情報発信のほか、船橋駅前インフォメーションセンターでは指さし確認シートの活用など、コミュニケーションに工夫しながら情報提供を行ってございます。また、外国人観光客に対する知名度向上と誘客促進に向けて、外国人の興味を引く店舗を掲載したリーフレットを作成し、成田空港内の観光案内所に配架することを予定してございます。
市といたしましても、本市の立地や資源を生かしながらインバウンド需要を取り込んでいくことは、地域経済の活性化につながるものと認識がございますので、SNSなども活用しながら、情報発信の充実に努め、外国人観光客に立ち寄っていただけるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
インバウンド対策は、単独の店舗や施設では効果的に進められず、地域全体で協力し、一貫した観光支援を提供することが重要です。地域経済の活性化を図り、外国人観光客のリピーターを増やすために、本市として全体の取組を強化することを要望します。
次に、高齢者等サポート事業、緊急通報装置の貸与、孤独死ゼロについて伺います。
まず、緊急通報装置の利用者の状況や本市としての支援体制との連携について、具体的にどのような取組がなされているのか。また、利用者が賃貸住宅に住んでいるか、所有不動産に住んでいるか。それぞれの件数について伺います。
[高齢者福祉部長登壇]
◎高齢者福祉部長(滝口達哉)
お答えいたします。
緊急通報装置を利用されている方の状況でございますが、心疾患や脳血管疾患、高血圧といった何らかの疾患がある方、過去に転倒歴があり連絡を行うことが困難になられたなど、常に安否の確認を必要としている方や、これらには該当しないものの、75歳以上で不安を抱えられている方など、令和6年11月末時点でおおよそ2,200人の方にご利用されております。
次に、市が実施する他の支援体制との連携でございますが、利用者のうち約65%の方は要介護の認定を受けており、各種の介護保険サービスを利用しているか。もしくは利用することが可能な状況であります。残りの35%の方は、要介護の認定を受けておりませんが、市で実施する軽度生活援助員や生活・介護支援サポーターの派遣事業による日常生活上の援助や寝具乾燥消毒、声の電話訪問といった様々なサービスを複数組み合わせご利用になられている方もいらっしゃいます。
緊急通報装置の利用者の方が賃貸住宅に住んでいるか、自己の所有する不動産に住んでいるかにつきましては、現時点で全数の把握には至っておりませんが、利用者の現況調査などの機会を捉え、順次把握に努めてまいります。
引き続き、利用者の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、今後も継続的な周知に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
緊急通報装置の利用者の方の現在の状況や、賃貸住宅にお住まいか、自己所有不動産にお住まいかなどを把握することは、身寄りのない高齢者等サポート事業との連携としても必要なことかと思いますので、調査、把握をお願いします。
身寄りのない高齢者等サポート事業は、先番議員の質問と重なるため、質問はせず、要望をお伝えさせていただきます。
本事業の対象要件として、市内の賃貸住宅に居住し、不動産を所有していない方、例外ありとされていますが、自己所有不動産に住んでいると家賃の未払いが発生しないため、大家や管理会社からの確認がなく、異変に気づく人がいないなど孤独死のリスクがあり、見守り支援が必要です。この要件により、自己所有不動産にお住まいの方が支援対象外と誤解し、相談を諦める可能性があります。
誤解を防ぐため、所有不動産に住む方も相談可能と明確に示し、広報や窓口対応で丁寧な周知を徹底していただければと思います。
所有不動産の整理については、リバースモーゲージの活用や不動産売却、遺言書作成など時間がかかりますので、賃貸に住んでいる、自己所有不動産に住んでいるなど区別をせず、不動産を所有している方も、まずは見守りサービスを開始し、伴走支援をしながら、不動産の整理を行い、死後事務委任契約を結ぶなど、誰も取り残さない孤独死ゼロの高齢者サポートの取組を要望いたします。
次に、金属スクラップヤード等対策について伺います。
医療センター移転予定地の近隣にはスクラップヤードが存在しており、市民の皆様から環境や安全面についての懸念の声が寄せられています。
まず、現在市内にはスクラップヤードが幾つ存在しているのか。また、千葉県においてスクラップヤードに関する条例が制定されましたが、市内のスクラップヤードについて不安を抱く市民の皆様の声に対し、市としてどのような対応が可能であるか伺います。
[環境部長登壇]
◎環境部長(岡田純一)
お答えいたします。
市内の金属スクラップヤードの数でございますが、現時点で17か所存在していることを把握しております。
続きまして、市内のスクラップヤードにおける市としての対応についてお答えいたします。
千葉県の、通称金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可取得につきましては、本市域内でも適用されるところでございます。市では、この条例の施行の前につきましても、市民の方から、スクラップヤードについてお問合せがあった場合は、関係部署が現地を確認するなど対応を行ってまいりました。
今後につきましても、定期的に保管基準違反のおそれなどスクラップヤードを監視するほか、市民の方から問合せがあった場合には、市廃棄物指導課が千葉県のヤード・残土対策課に協力して立入りを行うなど、必要な対応を行ってまいります。また、騒音・振動などの公害関係法令に関する不適正な状況を確認した場合は、市環境保全課で現地確認するなど、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
本市としても必要な対応を行っていただけるとのこと、安心しました。
次に、医療センター用地の脇を流れる念田川の土砂が毒性の強いタリウムに汚染されているとして、心配する市民の方々から、市に汚染源の調査を求める申入れ書が提出され、大きな懸念が寄せられております。
このような状況に対し、本市としてどのように対応していくのか伺います。
[環境部長登壇]
◎環境部長(岡田純一)
お答えいたします。
念田川周辺の金属スクラップヤードからの排水検査につきましては、水質汚濁防止法による特定事業場、または、有害物質貯蔵指定事業場に該当しないことから、排水を検査することはできません。市では、公共用水域の水質監視におきまして毎年の状況を比較検証できるように従前から定めている測定点で測定を行っております。調査項目につきましては、環境基準等で基準が定められている物質のうち、継続的に監視を行う必要のある物質を測定の対象としているところでございます。
なお、念田川の測定点では、念田橋で2か月に1度、下流の八栄橋、さくら橋では月に1度、水質調査のため採水に赴き、河川の状況を確認しており、現時点で当該水域に異常は認められておりませんが、引き続き、状況に応じて実施内容を見直しつつ、これらの監視及び調査を進めることで、公共用水域の水質の保全を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
医療センター用地の周辺ということでご心配をしている市民の方々がおりますので、安心していただけるように、より一層の監視と調査をお願いいたします。
次に、海老川上流地区土地区画整理事業、医療センター建て替えについて伺います。
土地区画整理事業について、協議の進歩の状況を伺う予定でしたが、先番議員が聞かれましたので、質問はいたしません。
助成金について、以下の点をお伺いします。
各年度における助成金の内訳はどのようになっているのか。既に支払いが完了している助成金について、その支払額及び支払時期はどうなっているか。使わなかった助成金についてはどのような取扱いとなるか伺います。
[都市計画部長登壇]
◎都市計画部長(杉原弘一)
お答えいたします。
海老川上流地区土地区画整理組合に対する市の助成金のうち、令和4年度の申請額4億8400万円の内訳は、調整池の築造費及び工事に支障のある建築物などの移転・除却に要する費用でありまして、関係機関との協議に不測の日数を要したことなどの理由により、全額を令和5年度に繰り越しました。
令和4年度申請分の実績につきましては、一部の施工が完了した1号調整池の築造費及び移転・除却費につきまして、令和6年3月に組合から完了実績報告書が提出され、令和6年5月に助成金4億8307万円を支払いいたしました。なお、この助成額が、現時点までに市が組合に対して支払いしている助成金の全額となります。
令和5年度の申請額8億4820万円の内訳は、調整池、宮前川、道路の築造費及び移転・除却費で、令和6年2月に助成金額を7億3380万円とする変更申請がございまして、その金額を令和6年度に繰り越しました。この令和5年度申請分につきましては、令和7年1月に内訳を調整池の築造費及び移転・除却費に、金額を2億7095万2000円とする2回目の変更申請がございまして、この内容が実績となる見込みでございます。
令和6年度の申請額15億1120万円の内訳は、調整池、宮前川、道路の築造費及び移転・除却費で、令和7年1月に助成金額を6億9340万7000円とする変更申請があり、この金額を令和7年度に繰り越す予定でございます。
令和7年度当初予算で計上している助成金10億4413万8000円の内訳は、調整池、宮前川、道路の築造費及び移転・除却費などを見込んでございます。
各年度の予算におきまして、当該年度中に支出した額及び翌年度に繰り越した額を除いた分は不用額となるものでございます。
以上でございます。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
助成金については、変更、繰越し、不用額などが入り混ざって分かりづらいので、誰が見ても明確に分かるように、申請書類や協議書などを整えていただくことを要望します。助成金については、引き続き注視し、質問していきます。
続いて、医療センターの建て替えについてです。入札不調を受け、今後のスケジュールをどのように見直すのか伺います。(予定時間終了2分前の合図)また、現在の病院の耐用年数や老朽化の状況を踏まえ、維持管理・修繕計画をどのように考えているのか。医療機能維持のための修繕の優先順位や具体策は何か。建て替えまでの課題と対策について、本市の見解を伺います。
[副病院局長登壇]
◎副病院局長(安孫子勉)
お答えいたします。
船橋市立医療センター等建て替え工事の入札が中止になったことを受け、スケジュールを含め事業の進め方について検討を行っております。現病院の維持管理や設備の更新修繕等については、これまで令和9年度中の開院を前提として、維持管理に係る委託契約や設備の更新修繕などを行う考えでおりましたので、今すぐに何か対応が必要となるようなことはございません。しかしながら、開院が遅れることとなりますので、今後の事業の進め方の検討と併せて必要な見直しを行ってまいります。
続いて、設備の更新修繕等の優先順位や具体策、建て替えまでの課題と対応策についてお答えいたします。
設備の更新や修繕などは以前より計画的に行っておりますが、移転建て替えを控えていることから、開院時期を見据え、可能な限り長く使っていくことを念頭に、部品交換などの修繕で対応できるものと、更新で対応するものの整理をしておりました。開院時期が遅れることになりますが、これまでと同じ考え方で更新修繕等の整理をしていきます。
しかしながら、例えば、特に老朽化への対応が課題となっている排水管など、根本的な改修を行うためには、工事中の使用制限が広範囲に及んだり、患者の受入れを一部制限したりすることが必要なものもあり、三次救急を担う救命救急センターとして24時間365日稼働している当センターとしては、対応が難しいものもございます。
このような設備等への対応といたしまして、現在でも日々、技術職員が目視による点検や調査等を行い、設備の老朽化や劣化等による腐食箇所等が確認された場合には、適宜不良箇所の交換や補修等を行っておりますので、引き続きこのような対応を行い、設備等の維持保全に努めてまいります。
以上です。
[中谷あやの議員登壇]
◆中谷あやの 議員
ご答弁ありがとうございます。
これまでも医療センターは修繕を重ねて設備の維持保全に努めてきたと思います。なるべく早く建て替えを実現するためには、柔軟な考え方が必要だと思います。入札の状況をお聞きしますと、建て替えが始まるまで2年~3年の時間があるようですので、その間に安心安全に一番早く建て替えが実現できる方法を新しい視点も入れて模索していただけるよう要望して、質問を終わります。
……………………………………………
出典 船橋市議会会議録