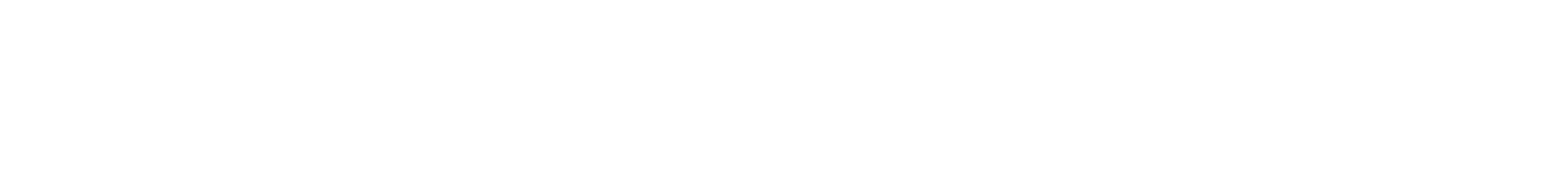一般質問 目次
船橋市議会の会議録へのリンク

一般質問のポイント
【若者支援・結婚新生活支援事業について】(要約)
<中谷> 要約
- 【人口動向の課題認識】
東洋経済の特集で、流山・八千代・袖ケ浦・印西市が若者に選ばれている一方、船橋市では25~39歳の人口が5年間で2.25%減少。交通利便性があるにも関わらず、若者に選ばれていない現状。 - 【住宅支援の現状認識を問う】
若年層・子育て世帯の住宅確保や定住支援の現状と課題について、市の認識を質問。 - 【結婚新生活支援事業の実績と周知】
婚姻届出件数に対し、制度の利用件数は少なく、8月末で35件・予算執行率20.5%。制度のさらなる周知を要望。 - 【若者支援施策の分かりにくさ】
複数部署にまたがる支援が、当事者には分かりにくくなっている現状を指摘。 - 【成人式での情報提供提案】
成人式を活用し、若者向け支援情報チラシ配布やLINE登録促進を提案。参加できなかった層には広報ふなばし等で周知を提案。 - 【全体像と連携の必要性】
支援全体像の「見える化」や担当者間の連携体制の構築を要望。
<答弁> 要約
- 【若年層の転入増を肯定】
20~29歳の転入超過が市の人口増に貢献しており、若年層が市の活力を担うと評価。 - 【住宅支援と事業導入の背景】
国調査に基づき、結婚における住居費負担を支援する目的で「結婚新生活支援事業」を開始。 - 【最新の実績】
令和7年8月末時点で助成件数35件、予算執行率は20.5%。 - 【若者支援情報の発信方針】
令和8年3月に策定予定の「船橋市こども計画」に若者支援施策を掲載予定。計画後は市HPやSNSで情報提供へ。 - 【連携と情報提供の強化に前向き】
各部署と連携し、分かりやすい情報発信体制の構築を目指す。
【高齢者支援について】(要約)
<中谷>
高齢化が進む中で、見守り・入退院手続き・金銭管理・死後事務など、終末期を支える公的支援制度の必要性が増しており、厚労省も新制度創設を検討している。本市の現状として、以下3点を質問:
- 65歳以上の人数・男女別・単身・高齢者のみ世帯数。
- 高齢者世帯の賃貸と持ち家の割合、緊急通報装置利用者の住居形態。
- 身寄りのない高齢者の人数把握状況。
<答弁>(高齢者福祉課)
令和7年4月時点で65歳以上は155,059人(男性67,502人・女性87,557人)。一人暮らし世帯48,822世帯、高齢者のみ世帯31,185世帯。持ち家率は要介護認定なし90.1%、あり78.5%。緊急通報装置利用者の住居形態については8月調査、10月末に集計予定。
<答弁>(福祉政策課)
身寄りのない高齢者は、保証人がいないと回答した割合が一人暮らし高齢者の約1割であり、推定で約5,000人と見込んでいる。
<中谷>
「身寄りのない高齢者等サポート事業」の安否確認(月1回の電話+半年に1回の訪問)だけでは急変時に対応できない懸念がある。緊急通報装置との併用や、他自治体で進むAI等の活用を含めた見守り体制の構築を求めるが、市の見解は?
<答弁>(高齢者福祉課)
高齢者のみ・一人暮らし世帯の増加を見据え、見守り体制の強化が必要。条件を満たす方には緊急通報装置の設置も想定。現行装置で活動状況は把握可能なため、直ちにAI活用の予定はないが、有効な手法は今後も調査していく。
<中谷>
対象者条件の文言に「不動産の処分を検討できる方」とあるが、まだ検討中の人が対象外と誤解しかねない。賃貸・持ち家問わず利用可能であること、死後事務は相談しながら進められることを明記すべき。また、リースバックなどの複雑な対応には専門機関との連携が必要と提案。
<答弁>(福祉政策課)
3つのサービス(見守り・入退院支援・死後事務)を一体的に提供。住居形態に関係なく利用可能。相談者の気持ちを丁寧に聞き取り説明。不動産所有者は契約前に方向性を決める必要があるが、契約までには複数回面談が必要(約3か月)。必要に応じて既存サービス(緊急通報装置)も案内。パンフレットにもわかりやすく記載予定で、信託銀行や不動産店などの専門機関を相談先として案内する。
<中谷>
市内の高齢者の多くが持ち家に住んでおり、本事業の主な対象者もそうなると想定される。一方、市民からは「条件が整ったら再相談して」と言われ、相談をためらったという声もある。相談しやすい表現・体制づくりと、誰一人取り残さない制度設計を強く要望。
【情報公開と説明責任について】(要約)
<中谷>
本市では新規・継続・拡大事業については議会報告がある一方で、事業の廃止・縮小については市民や議会への十分な説明がないケースがある。限られた財源を有効活用するには見直しも必要だが、その際の判断基準や影響評価、説明責任の透明性が重要である。
→ 廃止・縮小時に市民アンケートや意見聴取を行っているか、苦情件数の把握や理由の公表はしているかを質問。
<答弁>
令和元・2年度の行財政改革推進プラン時は見直し結果を公表したが、現在は所管ごとの対応に任されており、全体をまとめての公表は行っていない。苦情件数なども全体的に把握していないのが現状。
<中谷>
現状では事業の廃止や「予算要求なし」の判断について、議会・市民への明示的な報告がなく、理由の把握が困難。決算書だけでは意図的な廃止か単年度終了かも判別しづらい。
→ 他自治体では、横浜市が「事業見直し一覧」を作成し、福岡市も整理経緯を公開するなど、廃止・統合の「見える化」を進め、説明責任と議会のチェック機能を高めている。
→ 本市でも廃止・縮小・統合事業を一覧で報告する仕組みの導入を提案。
<答弁>
周知方法は事業の性質に応じて所管が対応していると考えるが、市民への影響が小さい場合など、議会への説明が行われていなかった例も把握している。
→ 今後は、横浜市の事例を含め他市の取組を参考に、廃止・縮小事業の周知の在り方を研究していく。
【海老川上流地区土地区画整理事業・医療センター建替えについて】(要約)
<中谷>
医療センター建替えは、入札不調により2〜3年間工事が着手できず、現在は赤字経営。この重大な情報を「広報ふなばし」で周知しているか、市民への情報提供の状況を質問。
<答弁>病院局
入札中止後、市議会議長やホームページ等で情報発信を行ったが、「広報ふなばし」での周知はしていない。経営状況は、議決後に広報やホームページで予算・決算情報を掲載。
<中谷>
重大なテーマであるため、「広報ふなばし」での特集掲載を要望。また、再検証にあたっては4つの柱について説明会開催と「パブリック・コメント」の実施も求める。
<答弁>病院局
説明会や出前講座、新病院建設Newsで市民に情報発信してきた。今後も議会・市民への情報提供に努め、「広報ふなばし」や説明会も含めて検討する。パブリック・コメントは基本構想時に実施済みで、現時点では予定なし。
<中谷>
今なら市民の関心が高く、より多くの意見が集まると期待できる。アンケートなどの手段でもよいので市民の声を丁寧に反映することを求める。現地建替えの再検証も必要と指摘。続いて1号調整池と念田川について協議状況を確認。
<答弁>都市計画部
全体の雨水排水計画は令和7年4月に協議が整い、現在は1号調整池を含む詳細協議を進行中。念田川の溢水対策も協議中。
<中谷>
1号調整池は工事未着手で、すでに6.7億円の助成金が支払われている。明確な完成見通しと協議の加速を要望。次に企業誘致の現状を質問。
<答弁>企画財政部
令和4年に市と組合で実現方針を策定。企業誘致は組合主体で、地権者と企業の合意で決定。現在は具体的な企業は未定で、構想に沿った事業提案を求めている。
<中谷>
企業誘致において市が受け身に見える場面もあり、災害対応・雇用・福祉連携も含めた視点が必要。市長が公約で推進を掲げているため、市が主導していると受け止める市民も多い。市と組合の連携を丁寧に説明し、医療と健康のまちづくり実現を求めて質問を締めくくる。