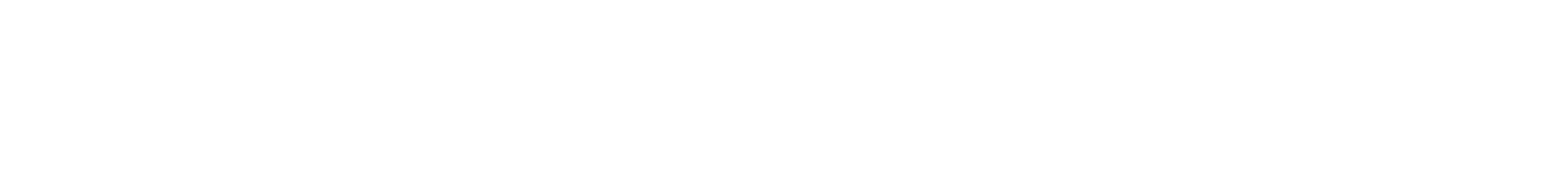内容をスキップ
船橋市議会の会議録へのリンク
船橋市議会会議録はこちらからご確認できます。
一般質問のポイント
【選挙の投票率向上の取り込みについて】
質問(中谷あやの議員)
- 他市では投票済証明書や来場証をキャラクター・デザイン性の高いカードにしてSNS拡散や話題づくりを実施。
- 柏市:「カシワニくん」+高校生美術部デザイン、提示で「センキョ割」適用。
- 市川市:「パンサーカード」=カードゲーム風デザインで若者・子どもに人気。
- 船橋市でも「ふなっしー」を活用したカラフルな来場証を導入すれば、投票率向上や話題性につながるのではないか。
- 柏市事例では1回の選挙あたり約15万円の予算で実施。
- 若年層を含む市民の投票参加促進のため、キャラクターデザイン証明書導入を予算化して検討してほしい。
答弁(船橋市)
- デザイン性のある投票済証明書や来場証を交付している自治体があることは認識している。
- 船橋市でも「せんきょ君」をデザインした来場証を希望者に交付中。
- デザインについては他自治体の事例を調査・研究する。
中谷要望
- 船橋市では既に「ふなっしー」を広報やパンフレットで活用しており、注目度が高い。
- 柏市では「カシワニくん」活用の投票済証明書を約15万円/選挙で実施。
- 民間でも「センキョ割」など投票促進の取り組みが拡大している。
- 若年層を含む幅広い市民の投票参加促進のため、キャラクターを活用したデザイン証明書導入を予算化して前向きに検討することを要望する。
【外国人との共生社会の実現と国保未納について】
質問
- 外国人への排外的言動に懸念。差別なく尊重し合える安心安全な地域づくりが必要。
- 外国人の国保未納は、制度理解不足や仕組みの違いから発生している。
- 厚労省は保険料前納制度導入や未納情報の在留資格審査反映を予定。
- 船橋市の外国人国保未納の現状(収納率・世帯数推移)と対応策は?
- 在留資格別の未納分析はしているか? 社会保険未加入の外国人への対応は?
- 国の制度改正への準備と対応方針を質問。
答弁(船橋市)
- 外国人世帯収納率:令和3年度60.15%(3,238世帯)→令和5年度72.16%(2,237世帯)に改善。
- 対策:6か国語パンフ、目立つ封筒、ベトナム語・ネパール語での電話催告、多言語タブレットで納付相談。
- 在留資格別の未納分析は未実施。
- 社会保険加入は雇用主の責任であり、市は働きかけしていない。
- 国の前納制度や情報連携は方向性が示された段階で、今後国の動向を注視し適切に運用予定。
要望(中谷)
- 外国人に関する在留資格・年齢層などの人口情報が各課で共有されていない。
- 関係課や関連機関と連携し、情報共有による支援体制構築を要望。
【起業・スタートアップについて】
質問(中谷)
- 女性起業支援に予算をつけてもらったことへの感謝。
- 7月開催の女性起業セミナーはデザイン性の高いチラシと内容で参加意欲を高め、実際に活発な交流が見られた。
- 職員も参加し、女性の起業ニーズ把握に努めていたことを評価。
- セミナーの参加人数・年齢層・課題、今後の女性起業支援の取組方針を質問。
答弁(船橋市)
- 7月12日のセミナー参加者は25名。年齢層は不明だが起業前の方が多く、グループワーク中心で実施。
- 課題は接客・集客、単身起業時の健康面リスクなどが多く挙がった。
- 商工会議所による「ふなばし起業スクール」や他部署の支援事業も実施中。
- 参加者アンケート分析や他自治体事例調査を行い、関係部署・機関と連携し必要な支援を検討していく。
【学びの多様化学校(不登校特別校)について】
質問(不登校支援の成果・課題と利用状況)
- 文科省は「学びの多様化学校(不登校特例校)」を提示し、千葉県内では浦安・習志野に設置、千葉市でも準備中。
- 船橋市でも不登校は年間1,400人以上で、多くが学びや社会的つながりを得られていない。
- 市長選公開討論会で市長は「現時点で設置の考えなし」と発言。
- これまでの不登校支援の成果と課題、サポートルーム・「夢のふなっこ」利用児童生徒の通学手段と人数(校種別)を質問。
答弁(教育委員会)
- 成果:教室以外の居場所が増え、校内教育支援センターで通えるようになった児童もいる。保護者からも好評。
- 課題:担当教員の負担増、個別学習支援方法、支援機関に関わっていない子への対応。
- 利用状況(令和6年度):
- サポートルーム:小40人(徒歩7・送迎31・公共2)、中61人(徒歩9・送迎16・公共36)
- 「夢のふなっこ」:小5人(徒歩1・送迎2・公共2)、中7人(送迎4・公共3)
- 家庭訪問のみ:小14人、中3人
質問(学びの多様化学校の認識・調査状況)
- 民間フリースクールは費用負担が大きく、公的制度で負担のない「学びの多様化学校」への期待が高い。
- 本市の認識と、これまでの調査・検討状況を質問。
答弁(教育委員会)
- 認識:不登校児童生徒が実態に応じた特別な教育課程で学べる学校。
- 調査:情報収集や視察で状況把握。近隣市では登校できる事例もあるが、定員30人以内などの課題あり。
- 本市は南北に広く通学困難な児童が出る可能性。
- 現時点では校内教育支援センターやサポートルームの充実を優先。学びの多様化学校は引き続き調査研究。
質問(将来の方向性と新たな支援手法)
- 文科省の定義に沿えば、サポートルームは校内教育支援センターに相当。
- 他市事例(さいたま市のメタバース活用と複数キャンパス)を紹介。
- 船橋市でもサポートルーム実績を活かし、オンラインやサテライトキャンパスで遠方生徒を支援する方法を要望。
市長への質問(不登校経験者支援の意義と取り組み方針)
- 不登校経験者大学生が運営する学習塾支援事例を紹介。
- 仲間との出会いや共感が人生を前進させる力になると強調。
- 不登校経験者・保護者の声を市長も直接聞き、社会とのつながりの選択肢を増やしてほしい。
- 本市の「学びの多様化学校」への考えを改めて質問。
答弁(市長)
- 学びの多様化学校は、不登校児童の通学支援に効果がある一方、定員が約30人と少なく、本市の広い地域で1か所だけ設置しても通えない児童が出るなどの課題がある。
- 理想は子どもが自ら通える距離に学びの場があることであり、保護者送迎にも限界がある。
- 現時点では、校内教育支援センターやサポートルーム(現在2か所)を拡充・拡大する方が有効。特に不登校児童が多い西部地区に新設を検討。
- 「学びの多様化学校」を否定しているわけではなく、最適な時期が来れば導入を検討する方針。
- 引き続き教育委員会と協議を続け、新たな取り組みも含めバランスの取れた支援体制を構築していく。
上部へスクロール